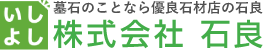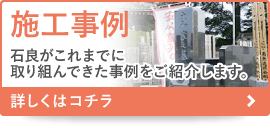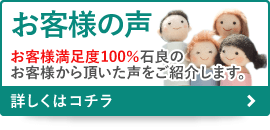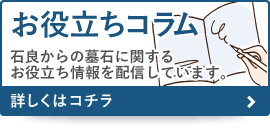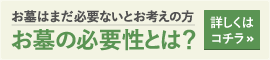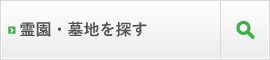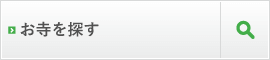戒名(かいみょう)は、亡くなった方が仏門に入ったことを表す大切な名前であり、仏教における故人の魂の行き先や位を示すものです。
しかし「どうやって戒名を付けるのか?」「自分でも考えられるのか?」「ランクや費用は?」など、分からないことも多いはずです。
この記事では、戒名の意味や構成、依頼方法や料金相場、自分で付けることの可否などを詳しく解説します。
目次
戒名とは何か?どんな意味があるのか
戒名とは、仏教において故人が仏弟子として新たに生まれ変わるために授けられる名前です。生前の名前(俗名)とは異なり、故人が仏門に入ったことを意味する霊的な名前として、葬儀や法要、墓石・位牌などに刻まれます。
戒名は、浄土宗・曹洞宗・真言宗・臨済宗・日蓮宗など各宗派によって構成や呼び方が多少異なりますが、いずれも「故人に対する敬意と供養の表れ」として重視されます。
戒名の基本構成と位の違い
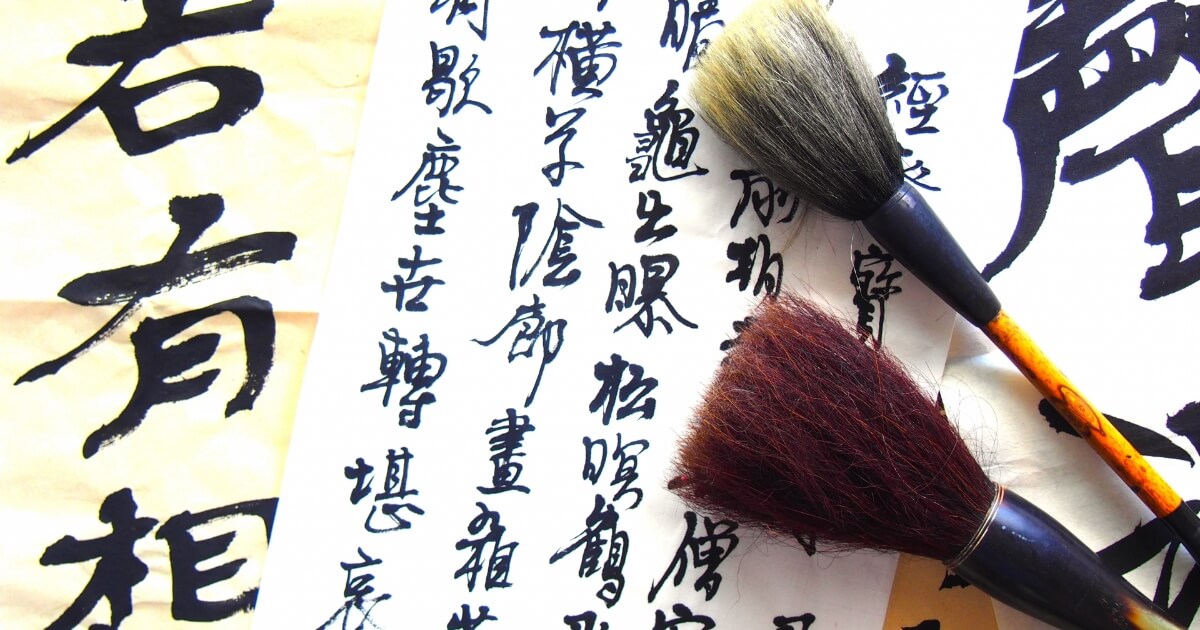
戒名には明確な構成があり、付け方にも一定のルールがあります。
一般的な構成要素
- 院号(いんごう):格式の高い称号。特別な貢献があった人や高額なお布施をした人に与えられます。
- 道号(どうごう):故人の性格や生前の活動に関連した言葉。個性を表す部分。
- 戒名本体(法名):仏教徒としての名前。2文字で構成されることが多く、男女や宗派によって用語に違いがあります。
- 位号(いごう):性別や年齢、地位によって使い分けられます(例:信士・信女、居士・大姉など)。
位の違いによる戒名の例
- 信士・信女:一般的な戒名の下位
- 居士・大姉:社会的地位がある人や高額なお布施をした人
- 院居士・院大姉:最上位クラス。院号が付き、格式が非常に高い
位によって戒名の格式や意味合いが変わるため、宗派や家族の希望に応じて慎重に選びましょう。
戒名の付け方と依頼の流れ

では、実際に戒名はどのようにして付けてもらうのでしょうか?依頼のタイミングや流れについて紹介します。
1. 誰が戒名を付けるのか?
基本的には、菩提寺(先祖代々の寺院)の住職にお願いすることが一般的です。付き合いがない場合は、葬儀社を通じて紹介してもらうか、宗派に準じた僧侶を依頼する形になります。
2. いつ依頼すべきか?
- 急ぎの場合は葬儀前
- 事前に準備する場合は生前戒名(寿陵戒名)として依頼
※近年では生前に戒名を用意する人も増えており、「自分らしい名前を選びたい」というニーズも見られます。
3. 戒名を付ける際に伝えるべきこと
- 故人の性格や人柄、趣味、職業
- 宗派
- 希望する位号(あれば)
- 家族の考え方(簡素なものでよいか、格式を重視するかなど)
これらを住職に伝えることで、個性や生き様を反映した戒名を付けてもらうことができます。
戒名の費用相場とランクの関係

戒名には明確な「料金設定」があるわけではありませんが、お布施という形で支払うのが一般的です。目安として、以下のような費用がかかることがあります。
- 信士・信女:3万〜10万円
- 居士・大姉:10万〜30万円
- 院号付き:30万〜100万円以上
あくまで目安ですが、位が高くなるにつれて費用も上がる傾向があります。ただし、住職や寺院によって費用の考え方は異なるため、事前に確認や相談をすることが重要です。
自分で戒名を付けることはできるのか?
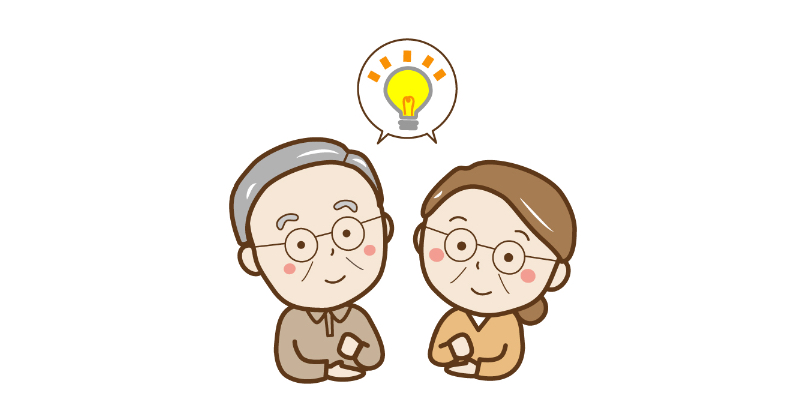
インターネットなどを見ていると、「戒名は自分でも考えられる」「自作できる」という情報もありますが、宗教的・儀礼的な観点から考えると慎重になる必要があります。
自作戒名のリスクと注意点
- 宗派の教義に反する可能性がある
- 菩提寺とのトラブルに発展する場合がある
- 墓誌・位牌への記載で認められないケースも
生前に希望がある場合は、住職と相談しながら作る「生前戒名」がおすすめです。自分の意思を尊重しつつ、宗教的にも認められる方法です。
まとめ
戒名は、故人が仏門に入るための大切な名前であり、人生の集大成を象徴するものです。構成やランクには宗教的な意味があり、依頼の際には故人の人柄や家族の思いを伝えることが大切です。
費用は位によって異なりますが、住職との相談で適切な形に整えることができます。安易に自己判断せず、仏教の教えや寺院との関係性を大切にしながら、丁寧に決めましょう。